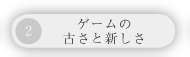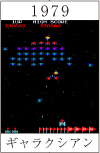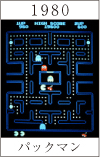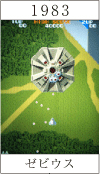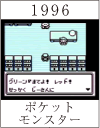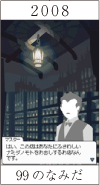日本人の「あそび」を大きく変えたビデオゲーム。しかし情報・メディア環境の変化、多様化とともにゲーム自体も変容し、「ゲーム離れ」という言葉さえ囁かれはじめた。このままゲームは衰退するのか、あるいは次なる展開がありうるのか? ゲームの処方箋プロジェクト研究員の河合隆史氏(早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授)、渡邊克巳氏(東京大学先端科学技術研究 センター准教授)、ビデオゲームにも詳しい香山リカ氏(立教大学現代心理学部教授)を迎え、人とゲームの新たな関係を考える。
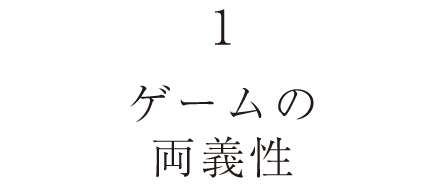
渡邊
もともと僕は河合さんと一緒に、
早稲田大学のこどもメディア研究所に参加していて、
メディアが子供に与える影響について調査・研究をしていました。
そこへナムコからゲームというメディアが人間に
どんな影響を与えているのか、調べてみませんかという話がきた。
僕自身、小さい頃はよくゲームをやっていて、
それが大人になった自分にどんな影響を与えたかというと、 確かによくわからないんですね。
一方、世の中を見るといわゆる“ゲーム脳”をはじめとして、
社会がゲームに対する態度を決めかねているような雰囲気もあって、何なんだこれはというのもあった。
ゲームは自分の専門の認知科学や実験心理学的に調べるには
いい素材でもあるなと思って、お引き受けしたんです。
早稲田大学のこどもメディア研究所に参加していて、
メディアが子供に与える影響について調査・研究をしていました。
そこへナムコからゲームというメディアが人間に
どんな影響を与えているのか、調べてみませんかという話がきた。
僕自身、小さい頃はよくゲームをやっていて、
それが大人になった自分にどんな影響を与えたかというと、 確かによくわからないんですね。
一方、世の中を見るといわゆる“ゲーム脳”をはじめとして、
社会がゲームに対する態度を決めかねているような雰囲気もあって、何なんだこれはというのもあった。
ゲームは自分の専門の認知科学や実験心理学的に調べるには
いい素材でもあるなと思って、お引き受けしたんです。

河合
ゲームは、周期的に悪影響論が出てくるといわれています。
しかし、ゲームをプレーする時、実際には、
いろいろな認知や情動体験をしているわけで、
それらを全て同じように良い悪いと決めつけてしまうことに対する疑問があった。
私の専門の人間工学という観点では、
短期的・直接的な影響という、比較的因果関係のわかりやすい実験系を組みやすい。
取り組むべき課題も多いので、
研究対象として非常に興味深いといえます。
しかし、ゲームをプレーする時、実際には、
いろいろな認知や情動体験をしているわけで、
それらを全て同じように良い悪いと決めつけてしまうことに対する疑問があった。
私の専門の人間工学という観点では、
短期的・直接的な影響という、比較的因果関係のわかりやすい実験系を組みやすい。
取り組むべき課題も多いので、
研究対象として非常に興味深いといえます。

香山
私は 1996 年に『テレビゲームと癒し』という本を出したんです。
ちょうど自分が精神科医になった 80 年代半ばに
家庭用ゲーム機が登場してきて、
私自身が社会人として病院に適応していく支えになったという個人的な話とともに、
その後 10 年くらいの臨床経験の中で、
主に思春期の患者さんたち、不登校児とか引きこもりとか、 もっと重症の統合失調症の子供たちとゲームを通して
コミュニケーションしてきたことについて書いたものです。
その時ゲーム悪玉論がいつ登場したのか調べたんですけど、 もうファミコンが登場したあたりからすぐに出ている。 一方では、日本を代表するすばらしいコンテンツだと 持ち上げられてみたり、非常に両極端な態度が ゲームに対しては混在していますよね。
ちょうど自分が精神科医になった 80 年代半ばに
家庭用ゲーム機が登場してきて、
私自身が社会人として病院に適応していく支えになったという個人的な話とともに、
その後 10 年くらいの臨床経験の中で、
主に思春期の患者さんたち、不登校児とか引きこもりとか、 もっと重症の統合失調症の子供たちとゲームを通して
コミュニケーションしてきたことについて書いたものです。
その時ゲーム悪玉論がいつ登場したのか調べたんですけど、 もうファミコンが登場したあたりからすぐに出ている。 一方では、日本を代表するすばらしいコンテンツだと 持ち上げられてみたり、非常に両極端な態度が ゲームに対しては混在していますよね。

渡邊
それはもともとゲーム自体が両義性をはらんでいるからですね。
ゲームをやっているときは楽しいけど、
ゲームが好きだと人に言うのはちょっと後ろめたい、
恥ずかしいという感情がある。
僕はその恥ずかしさ・後ろめたさはすごく重要だと思っているんです。